近年さまざまな業界で、「DX」「ICT」「IoT」という言葉をよく耳にします。介護業界も例外ではなく、これらに取り組んだり活用したりすることで、業務効率化や負担軽減につなげ、多くの課題を解決している現場が多数存在します。
しかし介護業務に携わる方の中には、「DX・ICT・IoT」という言葉を聞いても、違いがよくわからない」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、DX・ICT・IoTの用語について解説し、活用したり取り組んだりすることでのメリットや例などについて解説します。
目次
DX、ICT、IoTのそれぞれの意味は?
DXとは?
介護現場におけるDX化とは
DXの例
DXのメリット
DXのデメリット
ICTとは?
介護現場におけるICT化とは
ICTの例
ICTのメリット
ICTのデメリット
IoTとは?
介護現場におけるIoT化とは
IoTの例
IoTのメリット
IoTのデメリット
介護のICT化には、ココヘルパの導入がおすすめ
まとめ
■DX、ICT、IoTのそれぞれの意味は?
まずは、「DX」「ICT」「IoT」の3つの用語の意味を簡単に紹介します。
| DX | デジタル技術を活用し、ビジネスモデルや組織、プロセスなどを変革させること |
| ICT | インターネットを活用したコミュニケーション技術 |
| IoT | さまざまなモノをインターネットに接続する技術 |
【DXの意味】
DXとは「Digital Transformation」の略称で、直訳すると「デジタル変革」という意味です。デジタル技術を駆使して、ビジネスモデルや業務の形を新たなものへ変革させる取り組みのことをいいます。
【ICTの意味】
ICTとは、「Information Communication Technology」の略称で、直訳すると「情報通信技術」です。デジタル化された情報の通信技術のことであり、簡単にいうと「インターネットをつないで人と人が情報をやりとりする技術」という意味があります。
IoTとは「Internet of Things(モノのインターネット)」の略称で、直訳すると「さまざまなモノがネットワークを通じて情報をやりとりできる」という意味です。
■DXとは?

DXは、デジタル技術を活用し、ビジネスモデルや組織、プロセスなどを変革させることです。後述する「ICT」や「IoT」をはじめ、AIやビッグデータなどのさまざまな技術を活用して、新たなビジネスモデルの創出や企業風土の変革、レガシーシステム(過去の技術や仕組みで構築されたシステム)の脱却を目指すものです。単にデジタルツールを導入したり、古い仕組みをデジタル化したりする取り組みではありません。
具体的には、業務プロセスを改善したり、サービス品質を向上させたりする取り組みですが、それらを達成するために「ICT」・「IoT」を含めたデジタル技術を活用しています。そのため「DX」「ICT」「IoT」それぞれのメリット・デメリット、活用例などは、共通している部分があります。「ICT」「IoT」は技術を指している言葉であり、「DX」はそれらの技術を用いて変革していくことを意味しているという点が違いです。
介護現場におけるDX化とは
介護を提供する事業者は、入居者のためにより良いサービスを提供することと、スタッフの負担を軽減し働きやすい環境を作ることが求められます。これらを実現するために、抱えている人材不足の課題を解決することや、業務プロセスの見直しを図っていく必要があり、介護業界でもDXへの取り組みをしていなければなりません。
DXの例
介護現場におけるDXの取り組みには、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
- 事務作業のペーパーレス化
- 介護システムの統合
- ロボットによる介護業務のサポート
- 従業員の稼働状況の可視化
DXの事例としてよく挙げられるのが、ペーパーレスや介護システムの統合化です。ICT機器やIoT機器を導入することで、これまで手作業だった事務作業をデジタル化し、断続的だった管理システムを統合することで、業務効率化や品質向上を目指します。
DXのメリット
DXに取り組むメリットを見てみましょう。
- 変化に素早く適応できる
DXに取り組むことのメリットは、あらゆる変化に素早く適応できるようになることです。現在の社会は、景気低迷やインフレ加速などのようにめまぐるしく情勢が変化しています。企業はこれらの変化に適応して、絶えず変革することが求められています。
介護業界も例外ではありません。たとえば介護業界では少子高齢化に伴って、人手不足と介護需要の高まりから、スタッフ一人ひとりの業務負担が増大しているという問題があります。このような課題を解消し、長く経営を続けていくためにも、さまざまな技術を有効利用していくことが求められています。
- 生産性向上や効率化につながる
DXに取り組むと、生産性向上や効率化につながることがメリットです。これは後述する「ICT」「IoT」にも共通したメリットですが、人の手で行っていた単純な作業や管理業務をデジタル化することで、作業時間の短縮やヒューマンエラーの削減が可能です。スタッフの負担軽減や、サービス品質の向上にもつながるでしょう。
- 変化に合わせた柔軟な対応が可能
DXへの取り組みは、変化に合わせて柔軟な対応ができることもメリットの一つです。たとえば災害などの不測の事態があっても、デジタル化が進んでいれば離れた場所にいても入居者の状況を確認したりデータにアクセスしたりでき、さまざまな判断や対応ができるようになります。企業は災害などが発生したときに、損害を最小限に抑え、すぐに復旧させるための「BCP(事業継続計画)」を立てる必要がありますが、DXはBCP対策にも有効であるとして注目されています。
DXのデメリット
DXに取り組む必要性がある一方で、デメリットになる部分もあるため注意が必要です。
- DXに取り組むための人材が必要
DXを進める担当者やエンジニアを確保することが、課題となるかもしれません。人材不足が深刻化している介護業界において、新たな人材を採用したり教育したりする余力がなく、なかなか推進できないという企業は少なくないでしょう。
- コストがかかる
DXに取り組むにあたり、初期費用やランニングコストがかかる点はデメリットとなるでしょう。プロジェクトの推進や機器の購入、システムの構築などの必要があり、これらに関わる人件費や機器本体の費用、運用に伴うランニングコストなどが発生します。介護施設向けの助成金も様々ありますので、助成金を活用しての導入も有効な手段です。
- すぐに結果は出ない
DXへの取り組み方はさまざまで、企業にとって最適な方法を見つけ、効果を出すために試行錯誤が必要となります。またDXの取り組みが利益を生み出すまでに、数年かかるともいわれています。どのように改善していくかの検討や、設備の構築、運用が定着するまでにも時間がかかるからです。
一方で、長期的に見るとコスト削減にもつながる取り組みでもあります。導入コストと削減できるコストを比較して、最適な形での運用が求められます。
■ICTとは?

ICTは、インターネットを活用したコミュニケーション技術です。コミュニケーションという言葉が入っているとおり、コミュニケーションを主体としていることが大きな特徴です。単なるデジタル技術やデジタル化を図ることに留まらず、ネットワークを活用した情報共有やコミュニケーションが重視されています。
ICTとよく混同されがちな言葉である「IT」との違いについても見てみましょう。ITは「Information Technology」の略称であり、日本語では「情報技術」と訳されます。もともとは、デジタル化したデータを利用する技術や機器のことを「IT」と呼ぶことが一般的でした。しかしインターネットが普及したことでデジタルデータの通信量が増えたため、ITにコミュニケーション(通信)を加え、ICTという言葉が用いられるようになっています。
たとえば、メールやSNSなどのコミュニケーションツールや、クラウドサービスなどもICTの一つです。
介護現場におけるICT化とは
介護業界においては、「DX・ICT・IoT」の中で一般的なフレーズとして使われるのが、ICT
です。
IT化が進み、さまざまなものを電子化・機械化できることで、介護業界は大きな効率化が図れました。さらに技術は進歩し、ICT機器を導入することで、情報をスムーズに共有できるようになったりリアルタイムで異変を把握できたりと、さらなる業務効率化やスタッフの負担軽減が実現できるため、多くの介護現場で進められるようになっています。
ICTの例
介護現場で使われている、ICTの活用例を紹介します。
- 映像確認できるナースコール
- 情報共有・記録システム
- カメラやセンサーによる見守りシステム
- インカムによる情報共有
映像で確認できるナースコールを導入すれば、駆けつけなくても状況を判断でき、迅速かつ最適な対応ができるようになります。対応後はタブレットやスマートフォンからその場で介護記録をつけられれば、事務作業の手間を省き、リアルタイムで情報共有ができます。
またセンサーによる異常検知や自動通知などにより、入居者の異変にいち早く気づけるようになります。ICT化によって、無駄を省けることはもちろん、細やかなケアにもつながるでしょう。
ICTのメリット
ICT機器を導入することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 業務の効率化
これまで人の手で行っていた業務がデジタル化されることで、無駄な業務を削減し効率化を図れるようになります。作業時間の短縮やヒューマンエラーの削減などが可能です。
- スムーズな状況把握や情報管理
ICT機器を活用することで、情報をデジタル化し一元管理が可能となります。必要な情報を必要なタイミングで閲覧・記録ができ、情報収や作成に時間をとられることがなくなります。
- コミュニケーションの円滑化
ICT機器を用いることで、社内でのコミュニケーションが容易に行えます。1対1の通話やメールだけでなく、複数人とリアルタイムでつながれるため、確認や指示が迅速に行える、伝達漏れを防げるなどのメリットがあります。
ICTのデメリット
ICTのデメリットは、以下のとおりです。
- 既存のシステムから移行するのに時間がかかる
ICT機器の選定や導入に加え、スタッフが使いこなせるようになるまでの期間も想定しておかなければなりません。アナログな方式に慣れているスタッフが多いと、慣れるまでに時間がかかったり受け入れられなかったりする可能性もあります。システムを変更することでどのようなメリットがあるかを理解してもらうことや、慣れるまでのサポートが必要です。
- ICT機器の導入コストがかかる
DXと同じく、導入コストなどが発生する点も考慮しておく必要があります。しかしICT機器の導入により業務改善につながれば、コストカットできる部分も増えるでしょう。十分に費用対効果を検証することが大切です。
■IoTとは?
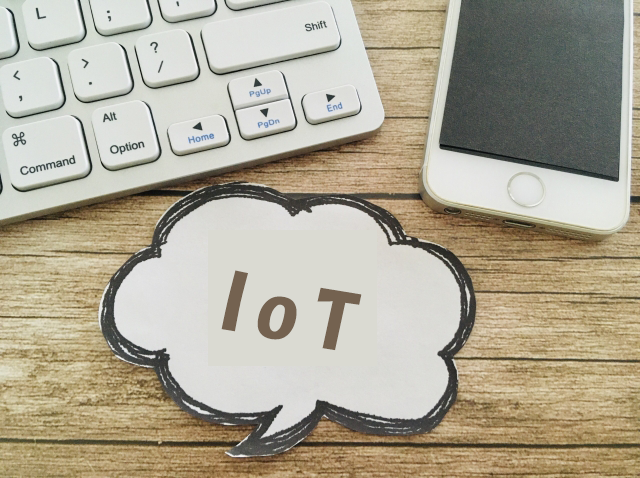
IoTは、さまざまなモノをインターネットに接続する技術のことです。
ICTが「インターネットをつないで人と人が情報をやりとりする技術」であることに対して、IoTは「あらゆるモノがインターネットにつながる状態や技術」のことを表します。身近なモノがインターネットにつながることで、データの収集や共有、コントロールが可能になり、新たなサービスや価値が生まれます。
たとえば、スマート家電やスマートウォッチなどがIoT機器の一例です。外出先から遠隔操作することや、話しかけるだけで操作することが可能になっています。また近年では生産工場の機械や、電車やバスなどの公共交通機関にもIoTが取り入れられて、遠隔地から状況を把握することや機械を制御することが実現しています。
介護現場におけるIoT化とは
介護現場においては、ICT化がもっとも一般的であり、IoTという用語はあまり使用されていません。しかし介護現場にとってもIoTの技術はさまざまな可能性を持ち、課題を解決できるとして期待されています。IoT化が進めば、さまざまな作業を自動化したり遠隔から操作できたりするため、業務負担を軽減し人材不足の問題解決にもつながるでしょう。
IoTの例
ICT導入例と重複する部分もありますが、以下のような例が挙げられます。
- 介護ロボット
移乗介助や移動支援をするだけでなく、AIが搭載されており、レクリエーションをサポートしたり会話できたりするものなど、さまざまなロボットが登場しています
- loTベッド
寝ているだけで入居者の睡眠状態や心拍数を自動で計測し、健康状態を遠隔から管理できるほか、危険につながる離床などの動作を迅速に察知できるIoTベッドがあります。
IoTのメリット
IoTのメリットは、ICTのメリットと同じく、業務効率化やスムーズな状況把握・情報管理、コミュニケーションの円滑化ができることです。インターネット技術を活用して、さまざまな方法で情報共有やデータ取得、遠隔からのコントロールができることから、人材不足の解消やサービス品質の向上にもつながるでしょう。
IoTのデメリット
IoTのデメリットも、やはりICTのデメリットと重なる部分がほとんどです。既存のシステムから移行するのに時間がかかったり、IoT機器の導入コストがかかったりする点は、注意が必要です。
■介護のICT化には、ココヘルパの導入がおすすめ
介護業界でもよく聞かれるようになったDX・ICT・IoTですが、その中でも一般的に使われる用語であり、導入が進められているのが「ICT」といえます。さまざまな業務をICT化することで、業務効率化やサービス品質の向上を図ることができ、その先のDXにもつながるでしょう。
介護現場のICT化に有効なのが「ココヘルパ」です。ココヘルパは、介護施設専用の無線式ナースコールシステムで、呼出機能のみのシンプルなモデルから、スマートフォンで呼出時の映像確認ができる最先端のモデルまで、幅広いラインナップを揃えています。スマートフォン・介護記録ソフトとの連携により、対応後にその場で介護記録をつけられるようになります。一連の作業が効率的に行えるほか、情報共有もスムーズに行えるようになります。
また多彩なセンサーを内蔵し、呼吸状態や睡眠、離床など、さまざまな変化を把握・察知できるモデルもあり、効率的で細かなケアが実現できます。すでに導入している他社の見守りセンサーとも連動ができます。

ココへルパはスマートフォンと連携できることで、状況変化に適応しやすい点も魅力です。たとえば、介護レベルの高い施設においては、最初からそのレベルに対応した機器を導入することもできます。介護レベルに応じた機器をカスタマイズできるため、断続的に機器を導入する必要がありません。長期的な使用が可能となることから、ICT機器の懸念点とされる導入費用も払拭できます。
現在ナースコールと介護記録システムやセンサーが連動していない場合や、PHSを使っているなら、ココへルパの導入で現場のICT化を図るのがおすすめです。
■まとめ
近年よく聞かれるようになった「DX・ICT・IoT」の用語について解説しました。とくに介護業界で導入が進んでいるのがICTです。
今回紹介したココへルパなら、業務の効率化やサービス品質の向上、スタッフの負担軽減などが実現するため、現場のさまざまな課題解決につながります。介護現場のICT化を進めたい場合は、ぜひココへルパの導入をご検討ください。

